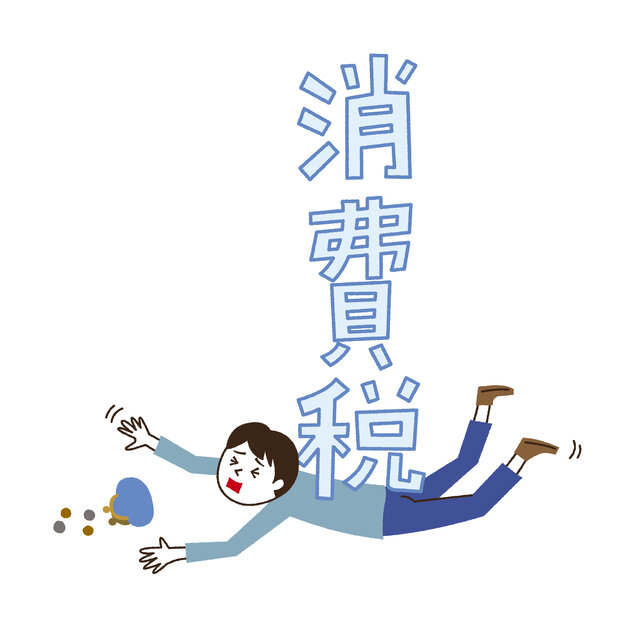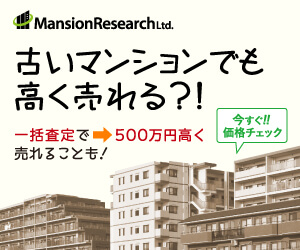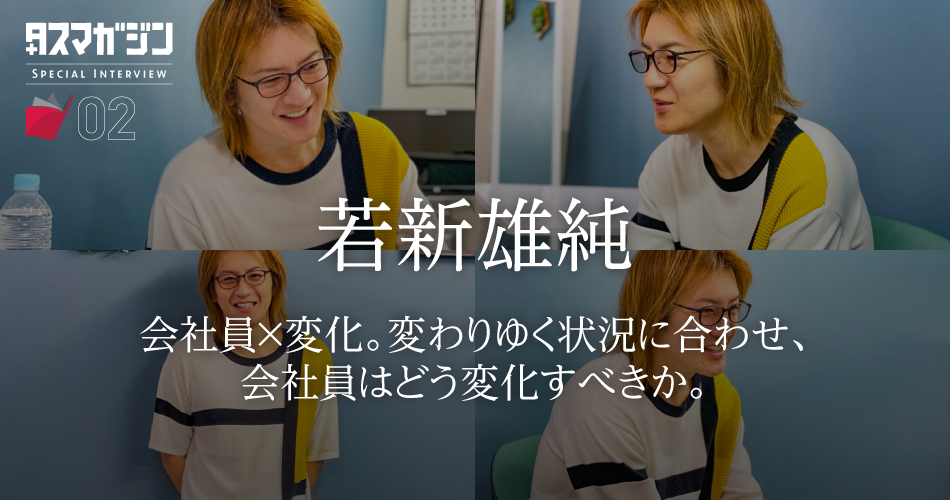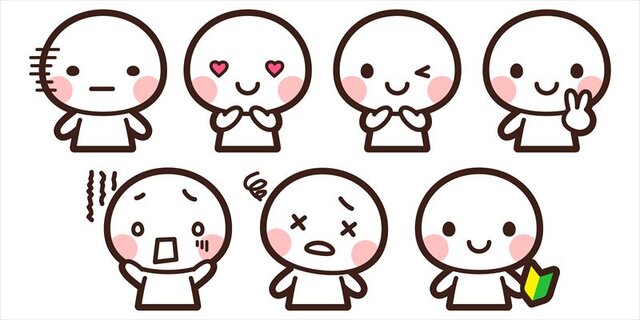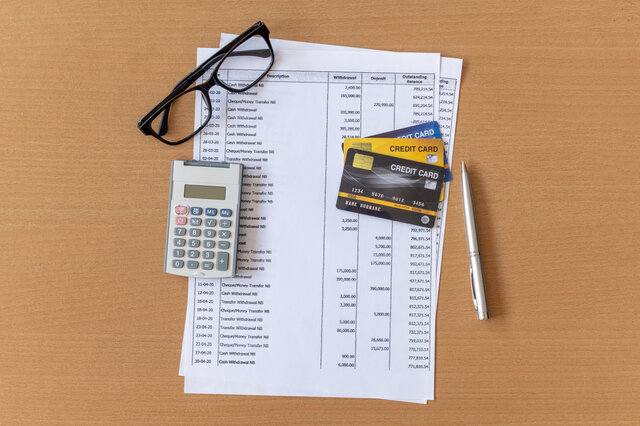
個人事業主が納める税金の種類とは?
税金ってそもそもどうやって決まるのでしょうか。簡単にいうと、その人の年収に対して課税される国税のことを「所得税」と呼びます。そして、住民票を入れている、自分が住んでいる地域で課される税金は「住民税」ですね。
税金はどうやって決まるの?
簡単にいうと、その人の年収に対して課税される国税のことを「所得税」と呼びます。そして、住民票を入れている、自分が住んでいる地域で課される税金は「住民税」ですね。
会社員として勤めている人の場合なら、所得税や住民税は会社が給料からの天引きという形で徴収して、会社経由で支払われます。
ということは、ほとんどの人は確定申告なんてものをしなくても、税金は勝手に支払われているということですね。
ところが、フリーランスや個人事業主はそうはいきません。自分が1年間に稼いだ収入から経費をまず差し引いて、どれくらいの収入があったのかを計算する必要があるんです。
そこで出てくるのが確定申告です。確定申告をするということは、その年度にいくらほどの収入があったのか、またその収入に対してどれほどの額の所得税を支払わなければいけないのかを判断し、算出された額の税金を国に納めないといけないということです。
確定申告をすることで、所得税だけでなく住民税も同時に確定することになります。
個人事業主が納める税金の種類について
所得税
そして、この所得税こそ、個人事業主の税金の内訳のなかでも最大の部分といえます。
個人事業主の場合ですが、収入から経費、控除額といった額を差し引いた「課税所得」に対して税金がかかります。
具体的な計算方法は「課税所得(収入−経費−青色申告特別控除−所得額控除)×税率−税額控除」となります。
1年間の所得税を計算し、翌年の2月16日~3月15日の間に税務署に確定申告書を提出しないといけません。
消費税
消費税の納税期限は3月です。
ですが、事業を開始してから2年の間、また過去2年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税を支払う必要はないのです。
このような条件があるので、多くの個人事業主は消費税を納める必要がありません。
住民税
また、住民税には「都道府県税」と「区市町村民税」が含まれていて、これは地方時自体に払うことから「地方税」とも呼ばれています。
それで、住民税の額を決める要素は、法人か個人か、さらに住んでいる地域によっても税額が異なることがあります。
個人事業税
現在、法律で定められた業務の種類は70種類あり、ほとんどの事業がこれに当てはまります。ただし、個人事業税は収入が290万円(事業主控除額)を超えなければ、支払う必要はないんです。
控除対象となる税金は?
所得控除
つまり、所得控除が多ければ多いほど、所得税が安くなるということです。所得控除にはいろいろ種類があるので、しっかり把握して適用してもらうようにしましょう。
社会保険料控除
金額に上限はありません。また、自分の保険料に加えて、配偶者などの家族の保険料を支払っている場合は、その分も所得から引いて計算することができます。
それで、家族の中で最も所得が高い人が、家族を代表して社会保険料を一括で支払うと、結果的に節税になります。
もし国民健康保険の場合には、保険料控除を請求するために、保険料納付証明書を提出する必要はありません。ですが、国民年金に支払った保険については、控除証明書が求められます。
医療費の控除
確定申告では、医療費控除という制度があり、1年間に支払った医療費のうち、一定額を超えた部分については所得控除を受けることができるんです。
ただし、これはあくまで所得控除の取り決めなので、支払った医療費が還付されるという意味ではありません。
ですが、正しく申告して制度を活用することで、一定額の回収を期待することができますよ。
ここで取り上げた控除の他にも、個人事業主が利用できる控除には「青色申告特別控除」「小規模企業共済等掛金控除」「扶養控除」「配偶者特別控除」など、さまざまな控除の取り決めがあります。