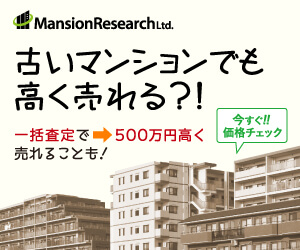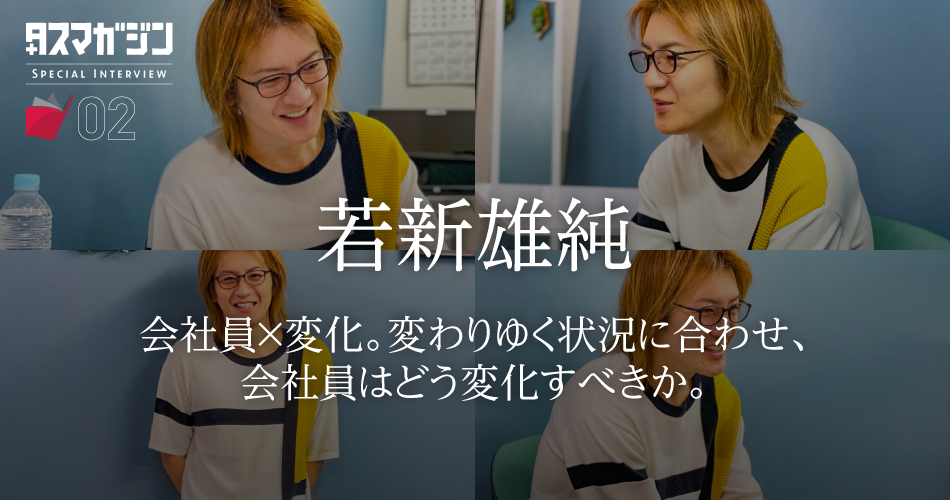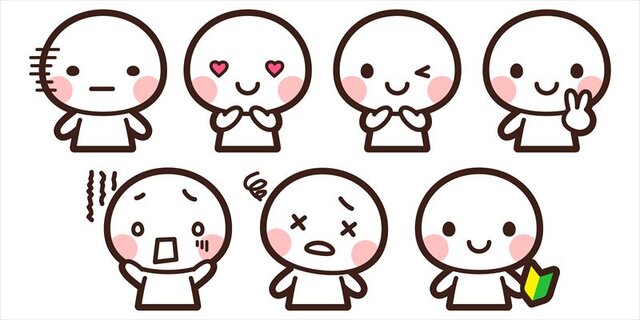正社員同士の共働き夫婦でする年末調整って配偶者控除って関係あるの?
この時期になると、毎年のように頭を悩ませるのが年末調整です。
特に夫婦共働き世帯においては、色々と面倒な手続きも多く、大変な思いをしていると思います。
面倒な年末調整の中でも特に面倒な配偶者控除についての情報をまとめました。
面倒な年末調整の中でも特に面倒な配偶者控除についての情報をまとめました。
配偶者控除とは
基本的には、年末調整などで還付金が返ってくる制度になるのですが、その対象は所得税だけでなく住民税にまで及びます。
ただし、結婚していれば誰でも利用できる物ではなく、いくつかの状況があります。
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
配偶者控除を受ける条件
配偶者控除を受ける条件は、収入が多い方の一年間の所得が1,000万円以下であること、納税者と結婚していること、納税者と生計をひとつにしていること、年間の合計所得金額が48万円以下であること、青色事業専従者として支払いを受けていないことなどがルールとなっております。
1,000万円以下の所得には、お給料だけでなく、事業所得なども含まれます。
配偶者特別控除との違い
配偶者控除は、103万の壁と言われている通り、決められた範囲を1円でも超えてしまうと、その恩恵を受けることができません。
そういった方のために、配偶者特別控除では、超えた金額によって控除額を徐々に減らしていくといった段階的な控除を実現するために生まれた制度になります。
2018年に配偶者特別控除を拡大する改正が行われ、多くの方が利用するようになっております。
共働き世帯の配偶者控除の活用方法
そのため、夫婦の両方が正社員としてバリバリに働いているような場合には、あまり意味のない制度となっております。
しかし、共働き世帯においても配偶者控除を使うことができるケースもあるみたいです。
片方の収入を調整する
例えば片方が正社員として働いていて、もう一方がアルバイトやパートタイマーだった場合には、配偶者控除を利用することができる範囲まで働く時間や日数を制限する必要があります。
途中で昇給したときなどには、改めて働く時間の調整が必要になります。
産休・育休中に利用する
それは奥さんが出産をする時です。
出産の時には、産前休暇と産後休暇を取ることができるのですが、その休暇の時期は、お給料が減ります。
その時期に配偶者控除を利用することができるレベルまで落ちているのであれば、パートナーの配偶者控除を利用すればよいのです。
配偶者控除は、一時的でも利用することができますので、翌年に産休が明けて普通に働けるのであれば、その年は利用しなければよいのです。
共働き夫婦の年末調整は保険料控除を上手に利用しましょう – 副業を頑張る人のお金の情報マガジン

小まめに情報収集をしていこう
そのため、自分達がどのような制度を利用することができるかを、しっかりと確認していかなければいけません。
とくに税金では、知らないと損をしてしまうことも多いので、定期的に情報収集をしていきましょう。