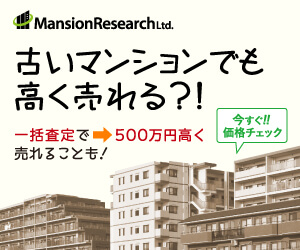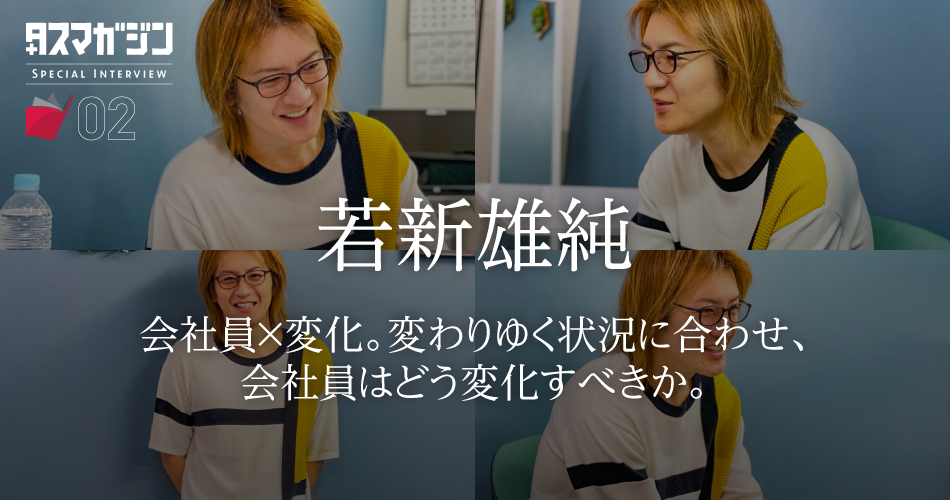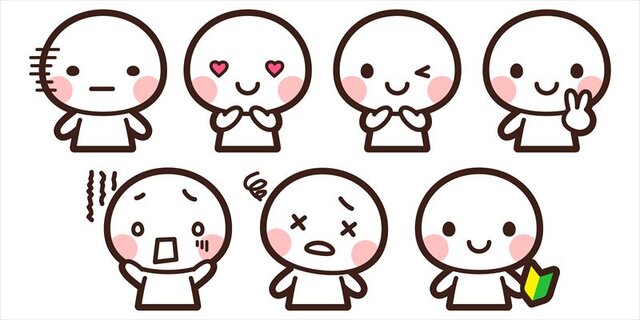個人事業で経営できる業種はなにがあるの?税金の種類についても解説!
あなたは個人事業で開業したいなと考えたことはありませんか?また個人事業でかかる税金にはどんなものがあるのか理解していますか?
ここでは個人事業で開業できる業種の紹介と、開業した後に支払う税金についてまとめました。これを読んで開業に向けて準備がしっかりと整っているのか確認の意味を込めて読み進んで下さい。
ここでは個人事業で開業できる業種の紹介と、開業した後に支払う税金についてまとめました。これを読んで開業に向けて準備がしっかりと整っているのか確認の意味を込めて読み進んで下さい。
個人事業で経営できる業種は?
代表的な自営業は8つあります。
飲食業
小売業(店舗・ネット)
理美容系事業
教育関連事業
コンサル事業
クリエイティブ事業
IT系事業
建設業
それぞれどのような自営業なのか説明していきます。
飲食業
平成21年総務省が行った経済センサス・基礎調査によれば、飲食店の数は 67万468店と多くの飲食業があることがわかります。
新しく出す店もあれば閉店する店があるなど、競争が激しい業種だと言えます。
小売業(店舗・ネット)
平成30年総務省から出された活動調査によると、平成26年時点での小売業の事業所数は99万246事業所と飲食業よりも多いのが数値として確認できます。
理美容系事業
令和元年、厚労省の発表によれば、理美容で自営している方の数は11万7266という数が存在します。
教育関連事業
学習塾や英語塾の他にも、料理教室や空手、柔道などスポーツの自営業も含まれます。
コンサル事業
この内容に当てはまる職種は、弁護士・司法書士といった国家資格を有するものや、最近ではインターネットでオンラインショップやブログでの売上を上げるためにコンサルを行う自営の方も増えてきています。
クリエイティブ事業
最初は会社に属し、自分のスキルを高め、独立して活躍している方が多く見られます。
IT系事業
近年はITに関する無料学習サイトやオンラインスクールで学習できるところが増え、その中にも独立を支援するところも数多く見られます。
建設業
2016年の国土交通省の調べでは、約47万事業所所在していることを明かしています。
開業しやすい個人事業主の種類
初期費用に必要な金額は業種によって様々ですが、個人事業を開業にあたり共通して必要な手続きがあります。
・税務署へ開業届を提出
・店や事務所の名前である「屋号」
・所得税の青色申告承認申請書
この3つはどの業種でも必ず行わなければいけない作業です。また従業員を雇用する場合、社会保険の加入手続きも必要です。
これらを踏まえた上で自営業を開始できますが、費用があまりかからず開業しやすい職業を紹介します。
IT事業
これからの時代はAIを使った事業が数多く展開することが予想され、その分IT関係に携わる方を重宝するといっても過言ではありません。
システム開発やプログラミング、コンサルを行うので、仕入れや在庫管理を行う必要がなく、初期費用を必要最低限で抑えられるので、開業しやすい職業の一つです。
クリエイティブ事業
クラウドソーシングを通じて業務委託という仕組みもあるため、自らが作成したポートフォリオを使ってネット上で提示できるので、営業もしやすいといったメリットもあります。
小売業(ネット販売など)
また、Amazonや楽天といった大手の元でモール出店をしたり、自分でサイトを立ち上げて、作成した作品を販売している方もいます。開業しやすい反面、集客や商品セレクトで苦戦する方も多いので、副業から初めて少しずつ軌道にのってから独立する方法をとるのがおすすめです。
教育関連事業
開業する方のことを指します。
自宅や施設の一室を借りて教室を開く方もいれば、コロナ渦で外に出れない方のためにオンラインで教室を開いている方もいるので、初期費用を抑えて開業することが可能です。
個人事業主が払う税金
個人事業で支払う税金は全部で4つあります。
・所得税
・住民税
・事業税
・消費税
それぞれがどの様な税なのかを詳しく解説します。
所得税
所得税の税額は、所得の合計から、寄附金控除や医療費控除などの「所得控除」を差し引き、残りの課税所得一定の税率を適用させて計算します。
①収入-必要経費=所得
②所得-所得控除=課税所得
③課税所得×税率-控除額=基準所得税額
④基準所得税額×2.1%=復興特別所得税
⑤①+②=所得税・復興特別所得税の額
所得税の税率は「累進課税率」といって、所得が高くなればなるほど税率が高くなる仕組みになっています。
かけられる税率と控除額を表にまとめました。
| 課税される所得税 | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
住民税
所得税と同じように所得に対する税金ですが、住民税の場合は、前年の所得に対して1月1日から現在の住民地で課税されます。住民税の金額は「所得割」と「均等割」の合計額です。
所得割とは、1月~12月までの所得に税率をかけて計算されたものです。均等割は前年の所得が一定以上となる場合は課税が一律となります。自治体のホームページで金額を確認できます。
事業税
事業税が課せられる条件として
・個人事業主であること
・所得が290万円以上
・該当事業を行っていること
があげられます。
該当事業というのは3つに細分化されます。
・第1種事業:税率5%
・第2種事業:税率4%
・第3種事業:税率5%
第1種事業は幅広く、飲食・物販・マスコミ・不動産がこれにあたります。
第2種事業は、畜産業、水産業、薪炭製造業です。
第3種事業は医療関係、税理士といった国家資格や専門資格が必要な業種となります。
消費税
事業者が支払う消費税は「原則課税方式」か「簡易課税方式」のいずれかで計算します。原則課税方式というのは、年間を通じて預かっている消費税から、支払った消費税を引いた金額です。簡易課税方式は、基となる期間内の課税売上高が定められた金額を下回る場合に選択できる計算式です。
個人事業を開業するにあたり、負担する税金を理解しましょう
個人事業で開業できる職種は8つあります。
飲食業
小売業(店舗・ネット)
理美容系事業
教育関連事業
コンサル事業
クリエイティブ事業
IT系事業
建設業
中には専門性を持った高いスキルを必要とする職種もありますが、日頃の仕事で培った能力や趣味で養われたスキルもあると思います。そのスキルを生かして個人事業で存分に発揮できるのではと思います。
また開業した後、支払わなければいけない税金は4つあります。
所得税
住民税
事業税
消費税
開業するにあたり初期費用もかかりお金がかかりますが、売上高に応じて支払う税金も比例して上がります。税金の仕組みもしっかりと理解した上で開業できるように知識をつけ準備をしましょう。