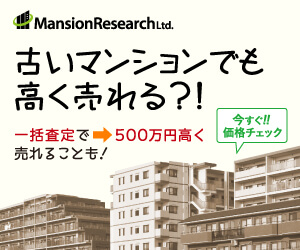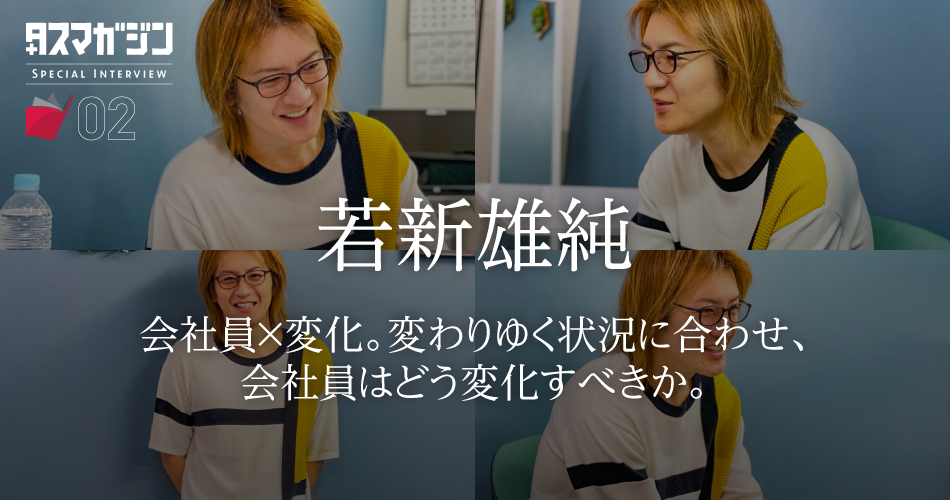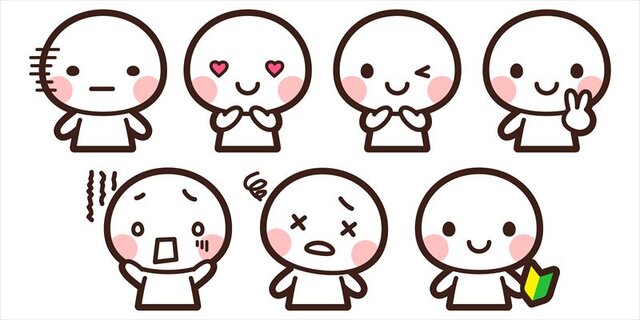意外と身近な存在である贈与税とは?簡単に解説!
日本には数多くの税金がありますが、馴染みがなく名前だけ知っている税金も多いでしょう。贈与税もその中の一つであり、普通に生活しているとなかなか耳にしない税金です。
ここでは、意外と身近な存在の税金である贈与税について簡単に紹介します。申告方法や、計算方法、注意点なども紹介するので、万が一に備えて必ず知っておきましょう。
人から財産や土地をも贈与した時に贈与税が発生する
保険金などの現金や、土地を贈与ときに贈与税が発生します。贈与税とは、贈与者が財産を受贈者に渡して初めて発生する税金です。受贈者は自分で申告して贈与税を納めなくてはなりません。
毎年1月1日から12月31までの1年間を区切りとして、総額が対象になります。しかし「暦年課税」と言って、110万円以内であれば基礎控除が発生するので税金がかかりません。
1年間で贈与した金額が110万円以上か以下で贈与税が決まる
極端な話、1年間毎日3人の人から1,000円ずつもらっても109万5,000円であるため贈与税が発生しません。しかし、1年間うち1日でも200万円贈与された場合は贈与税が発生します。総額200万円の場合は、110万円を超えた90万円に贈与税が発生します。
相続税との違いは何?
贈与税と似ている税金で、相続税があります。どちらも人に対して財産を譲る点で共通点があるので混同してしまう人もいるかもしれません。違いは明確にあり、贈与税と相続税の違いは「発生原因」です。
相続人が死亡して発生するのが「相続税」で、贈与者と受贈者が話し合って決めて贈与した場合が「贈与税」です。また、血縁関係の有無が問われるのが相続税で、問われないのが贈与税です。
さらに違う点は「税率」です。相続の場合は、「絶対に」財産を譲らなければならないので、税率が低く設定されています。反対に贈与税の場合は、話し合いで決定するものなので、税率が高く設定されています。
贈与税の計算方法は?
贈与税は受贈額が増えると税率が高くなる「累進課税」です。つまり、贈与された金額に応じて納める税金が多くなります。
一般贈与の税率と贈与税が発生する例を出すので確認してみてください。
贈与税の一般税率
左から、基礎控除後の課税価格、税率、控除額を意味しています。税率を見てみましょう。
・200万円以下 / 10% / なし
・300万円以下 / 15% / 10万円
・400万円以下 / 20% / 25万円
・600万円以下 / 30% / 65万円
・1000万円以下 / 40% / 125万円
・1500万円以下 / 45% / 175万円
・3000万円以下 / 50% / 250万円
・3000万円以上 / 55% / 400万円
少額のうちは細かく設定されているのに対し、高額になるほどある程度の金額で設定されています。例えば、600万円贈与されたとします。600万円から基礎控除を引くので課税対象になる金額は490万円です。
600万円-110万円=490万円です。一般税率を確認すると、600万円以下に該当されるので、30%の税率がかかります。計算してみましょう。
490万円×30%=147万円です。そして、600万円以下の場合は、65万円の控除額が設定されているので、最終的な金額は以下になります。
147万円-65万円=82万円ですね。つまり、82万円を贈与税として納めます。
特例贈与の扱いになるケースもある
例外として、親や祖父母が子供や孫に贈与した際は特例贈与扱いになります。税率が低く設定されているので、贈与税を抑えられるのが特徴です。
しかし、子供や孫が贈与を受け取った年に20歳以上である必要があります。
特例贈与の税率
一般贈与同様に、左から、基礎控除後の課税価格、税率、控除額を意味しています。税率を見てみましょう。
・200万円以下 / 10% / なし
・400万円以下 / 15% / 10万円
・600万円以下 / 20% / 30万円
・1000万円以下 / 30% / 90万円
・1500万円以下 / 40% / 190万円
・3000万円以下 / 45% / 265万円
・4500万円以下 / 50% / 415万円
・4500万円以上 / 55% / 640万円
となっています。200万円以下だけが一般贈与と同じですが、他の税率と控除額は全て違いますね。先程の例を、特例贈与に当てはめてみましょう。同様に600万円贈与されたとします。
課税対象になる金額は490万円で変わりません。しかし、特例贈与の場合は税率が20%に変更されています。
490万円×20%=98万円です。そして、30万円の控除があるので、最終的に納める税金は以下です。
98万円-30万円=68万円です。特例贈与は血縁関係がなければ発生しませんが、一般贈与と比較すると14万円も差があります。
贈与税の申告方法は?
計算方法が分かったので、申告方法についてご紹介します。贈与税が発生する贈与があった場合、申告は翌年の2月1日から3月15日までの間に受贈者住所を所轄する税務署で行います。暦年課税であれば「贈与税の申告書」相続時精算課税であれば贈与税の申告書に加えて「相続時精算課税選択届出書」を作成して提出しましょう。
ちなみに、納付方法は現金です。

あまり認知されていないが夫婦にも贈与税が発生する
生活を共にしている夫婦だと財産の感覚がなくなってしまいますが、原則として夫婦間でも贈与税が発生します。当然、110万円以下では納税の必要がありません。しかし、110万円を超えた場合は、贈与税が発生するとは知らなかったでは済まされず、名義が残っている場合などは税務署から贈与税を納めていないと認識されてしまうでしょう。
しかし、夫婦間で発生する贈与税は少々特殊です。贈与税がかかるケースとかからないケースを見ていきましょう。
高額なプレゼントを贈った時は110万円以上に気をつける
夫婦間でプレゼントを贈り合って110万円を超えた場合は、贈与税が発生します。例にすると、200万円のアクセサリーを買った時などは90万円が贈与税の対象です。アクセサリーは生活費と関係がないので贈与税が発生すると分かりますが、車のように問題視されている贈り物もあります。
普通の車であれば生活に必要であるため贈与税が発生しません。しかし高級車の場合はどうでしょうか。生活に必要な車を高級車にする必要性はあまりないと言えます。したがって、高級車を夫が買って名義を妻の名前にすると贈与と認識されてしまう可能性があります。
生活費として使わなかったお金にも贈与税が発生する
夫から受け取った生活費で指輪やネックレスなどのアクセサリーを購入した場合は生活費と何ら関係がありませんので、贈与税の対象になります。当然、自分の収入で株や金融資産を購入するのは問題ありません。
しかし上記のケースにあてはまらない場合は、基礎控除内の金額にとどめておく対策が必要です。
生活費や養育費に該当するものは贈与税がかからない
扶養義務者から生活費や養育費に充てている財産は贈与税がかかりません。旦那から毎月数十万円の生活費を受け取っていても贈与税が発生しないのは生活費に該当しているためです。
しかし、生活に必要のない高額なものを渡している場合は贈与に該当する可能性があるので、ほどほどにしなければなりません。
贈与税に関する注意点はある?
贈与税に関する注意点をご紹介します。贈与税が発生した場合、スムーズに納税して終了すればよいのですが、認識の間違いなどで税金を納めなくてはならないケースがあります。
財産や土地の受贈者となる場合は、以下に注意しましょう。
年間110万円以下なのに定期贈与だと見なされてしまったケース
110万円以下なら非課税と毎年暦年贈与していたケースです。税務調査によって「定期贈与」と見なされてしまうと贈与税が発生します。
定期贈与とは、定期給付を目的とする贈与です。例えば、2,000万円の財産を子供に20年かけて贈与していて、毎年110万円以下に収まっているとします。しかし、2,000万円を分割して支払っただけだと税務署に判断された場合、2,000万円以下の贈与税が適用されます。
一見、年間110万円以下で何も問題ないように見えますが、コンスタントに贈与をしている場合は注意してください。毎年違う時期に贈与したり、毎年違う金額を贈与したりして対策を取らなくてはなりません。
膨大な金額の場合は、定期贈与と見なされないようにしましょう。
暦年贈与が有効にならなかったケース
子供の口座名義人とする預金口座を作って、贈与のつもりで毎年入金していたケースは、子供の預金口座が名義預金として判断されるケースがあります。名義預金とは、預金口座の名義人と本当の預金者が異なる預金を指しています。
名義預金だと判断された場合、贈与ではなく親の預金だと見なされるケースがあるので相続税の対象になるのです。自ら口座を開設して口座の管理をするなどの対策をしましょう。
1人につき110万円だと勘違いをしているケース
1年間に受け取れる非課税範囲の金額が110万円であって、1人につき110万円ではありません。父と母が子供に毎年110万円贈与していた場合、子供は年間で220万円贈与されているので、贈与税が発生します。
少しだけ間違っていた場合でも贈与税を納税しなければならないので、贈与の際はよく確かめてから行いましょう。
贈与税の発生に備えておこう
贈与税の基礎について簡単に解説しました。日常的に発生する所得税や住民税などと違って、ピンポイントで発生する税金なので、耳馴染みがないのは当然かと思います。
しかし、税金は生きていく上で必ず関係するものであり、贈与税を支払う機会がくるかもしれません。いつでも対応できるように、贈与税についてしっかりと理解しておきましょう。