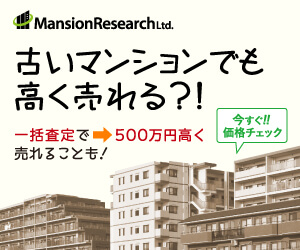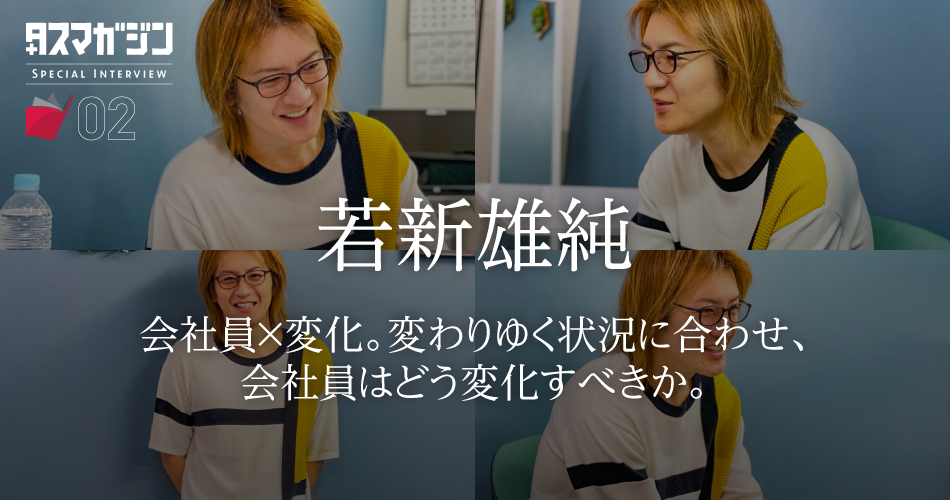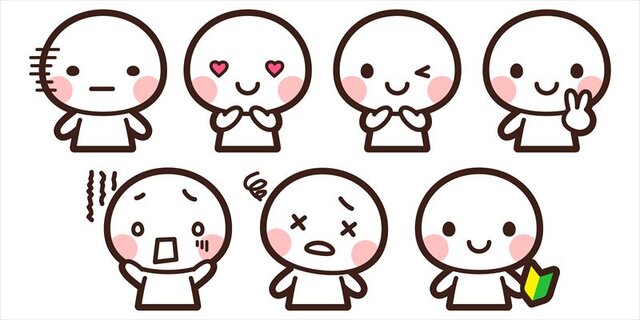ボーナスとは?種類・支給日・支払い回数・額の決め方などを理解しよう
働くうえで重要なのは、会社からもらうお金でしょう。会社から支給されるお金は、給与とボーナスに分けることができます。
新入社員など若い世代の人は、もしかしたらボーナスの基本がわからないかもしれません。名前は聞いたことがあっても、詳しい事情を知らない人もいるでしょう。
ここでは、ボーナスの基本的なことから、種類・支給日・支払い回数・額の決め方・年齢別平均支給額を紹介します。
ボーナスを賢く活用するため、基礎情報を知り役立ててみましょう。
新入社員など若い世代の人は、もしかしたらボーナスの基本がわからないかもしれません。名前は聞いたことがあっても、詳しい事情を知らない人もいるでしょう。
ここでは、ボーナスの基本的なことから、種類・支給日・支払い回数・額の決め方・年齢別平均支給額を紹介します。
ボーナスを賢く活用するため、基礎情報を知り役立ててみましょう。
ボーナスとは?
そもそもボーナスを支払う決まりはなく、会社によって基準が異なります。ボーナスは会社が利益を上げた際に、従業員に還元する給与だと考えておきましょう。従業員のモチベーションアップに役立っています。
日本におけるボーナスの始まりは、江戸時代までさかのぼります。季節に応じた着物支給の習慣や、正月に配る氷代や餅代などが始まりとされています。現在のボーナスは現金での支給が一般的です。
ボーナスの種類
基本給をもとにしたもの、業績に応じて変わるもの、決算に合わせた支給です。それぞれどのようなボーナスの種類なのか詳しく紹介していきます。
基本給連動型賞与
ボーナスの支給額の基準が基本給で、「給与の〇か月分」という計算方法です。
何か月分が支給されるかは、その会社によって異なります。会社の規約で決められていれば、従業員もどのくらいのボーナスがもらえるのかわかりやすいでしょう。
注意が必要なのは、手取り額ではなく基本給である点です。毎月もらっている給与には、たくさんの手当てが付けられています。給与の額が高くても、基本給が低ければボーナスの額も少なくなるでしょう。
業績連動型賞与
業績に応じて変わるボーナスは、頑張るほどボーナスの額がアップします。勤続年数や年齢に影響されることはありません。新入社員であっても業績を上げればボーナスの額がアップするため、モチベーション向上に役立ちます。
会社にとっても、固定のボーナス費用がかからないため、経費削減になる場合があります。ただし、業績を上げられなければボーナスの額は減るため、従業員にとって公平とはいえません。日本では給与連動型が多いのに対し、海外では賞与連動型が多い傾向にあります。
決算賞与
1年の利益を確定させ会社の業績がよければ、利益分が従業員に分配されます。給与連動型や業績連動型とは別に、決算賞与を設けている会社もあるようです。
決算賞与を設ける理由は、会社にとって法人税の節税対策になるためです。従業員に支払ったボーナスは損金扱いにできるため、結果的に利益が減り節税効果があります。また、従業員にとっても決算賞与があると、嬉しいボーナスでしょう。
決算時期は、会社ごとに自由に決めて問題ありません。3月の決算が多いのですが、9月や12月のところもあります。
ボーナスの支給日
公務員はボーナスに対する法令があるため、従う必要があります。会社員の場合は、それぞれの会社の基準により支給日が変わってくるでしょう。
公務員
公務員のボーナス支給日は、年に2回です。
夏は6月30日、冬は12月10日の決まりがあります。
毎年変動することがなく決められた日にボーナスが支給されています。ただし、支給日が土日に重なる場合は、直前の金曜日が支給日です。
地方公務員の場合は、自治体により多少支給日に変動があります。いずれにしても国家公務員の支給日と同じ日か、近い日に支給されるでしょう。
会社員
いつが支給日だと明確にすることは難しいのですが、大体の目安はあります。
夏は6月下旬~7月上旬までで、冬は12月中旬が多いようです。春に支給する場合は4月頃で、決算賞与なら3月頃になるでしょう。
会社によってはボーナスを支給しない場合もあるため、会社の規約を確認しましょう。また、ボーナス支払い規約があっても、支給に条件を設けている場合があります。例えば在籍要件では、支給日に在籍する人だけが対象となるなどの規約です。
ボーナスの支払い回数
支給回数による取り扱いが違うのは、社会保険料の計算方法によるためです。社会保険料とは、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料のことです。ボーナスが4回以上の支給だと給与扱いになり、ボーナスにかかる保険料の算出と変わるためです。
ボーナスが4回以上支給される場合は、3回までと比べて社会保険料が安くなります。また、傷病手当金や出産手当金が大きくなるメリットもあります。ただし、同じボーナスを年4回以上支給することが、規則などで定められていることが条件です。
夏と冬の2回
前述したとおり、夏は6月下旬~7月上旬までで、冬は12月中旬が多いでしょう。
年3回
会社によっては、夏と冬のボーナス以外に、奨励金や決算賞与を支払う場合があります。
ボーナスの額の決め方
それぞれどのように計算されているのか知っておきましょう。
公務員
期末手当と勤勉手当は、それぞれ地域手当や扶養手当を含む月額給与が基準となります。月額給与+地域手当+扶養手当に支給月数をかけたものです。
期末手当と勤勉手当は支給月数が異なります。
会社員
・定額方式
・給与連動方式
・利益分配方式
そもそもボーナスの支給は、結果を出した人に報いる考えや、会社の利益を従業員に還元する考えからあります。会社がどのような考えをしているかにより変わってくるでしょう。
さらにボーナス支給の基準は、終業規則・労働協約・労働契約などに明記されています。
日本で古くから採用されている方法が、給与連動方式です。「基本給の〇か月分」といった決め方がこのタイプです。
何か月分にするかは会社ごとに異なり、3か月分や2.5ヶ月分のように細かい規定にすることができます。
基本給とは、各種手当を引いた金額です。従業員の年齢や勤続年数、スキルなどの基準により基本給が決められています。例えば、前月の基本給が20万円で2か月分と決められていれば、40万円のボーナス支給です。
利益分配方式
利益分配方式は、最近増えている方法です。会社に貢献した割合に対し、利益を従業員に分配します。
どのような支給にするかは、スキル・評価・調節など会社によりさまざまです。
まずは、ボーナスの基本額を決めていきます。さらに基本額に加えて、従業員ごとの役職や資格などでスキルをプラスさせ、会社に貢献した割合で評価を決めていくなどの対応です。
従業員の年齢を考慮するときは、調整分でプラスさせることができます。
利益分配方式のメリットは、ボーナス決定が明確である点です。
一方で、会社の売上によりボーナス額が変わる方法だと、業績悪化でボーナス減額や支給されないデメリットがあります。
どのような基準で利益を分配するかは、よく考える必要があります。
ボーナスの年齢ごとの平均額
年齢ごとのボーナス支給額は、厚生労働省の「令和元年賃金構造基本統計調査」を参考にしてみます。
| 年齢 | ボーナス平均額 |
|---|---|
| 20~24歳 | 39万6,400円 |
| 25~29歳 | 69万6,400円 |
| 30~34歳 | 84万7,600円 |
| 35~39歳 | 96万2,700円 |
| 40~44歳 | 107万3,300円 |
| 45~49歳 | 118万9,500円 |
| 50~54歳 | 131万3,800円 |
| 55~59歳 | 125万9,400円 |
従業員の人数が少ない企業より大企業のほうが、ボーナス支給額が上がる傾向にあります。また、ボーナス支給額は50代をピークに、年齢が上がるごとに下がっていくようです。
ほかにも女性より男性の支給額が上がりやすく、中卒より高卒、高卒より大卒で支給額が上がる傾向にあります。
ボーナスの支給基準を確認しておこう
ボーナス支給に在籍基準がある場合は、支給後の退職がおすすめです。一般的には夏と冬のボーナス支給が多いため、その後に退職すれば、退職後の生活費や就職活動費に充てることができるでしょう。
働いている人もボーナスの基礎を理解して、計画的に支給額を使うようにしてください。