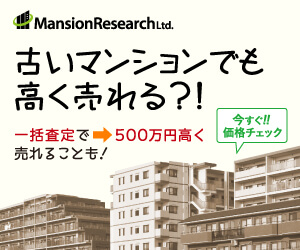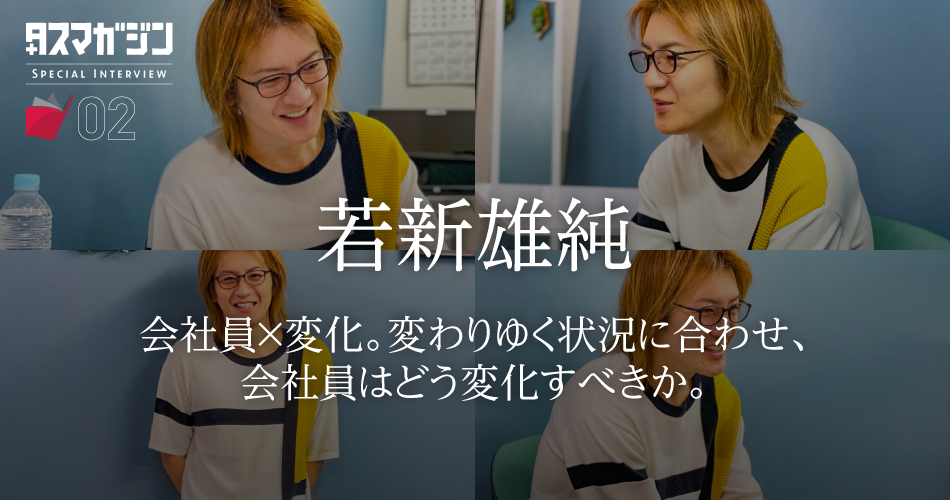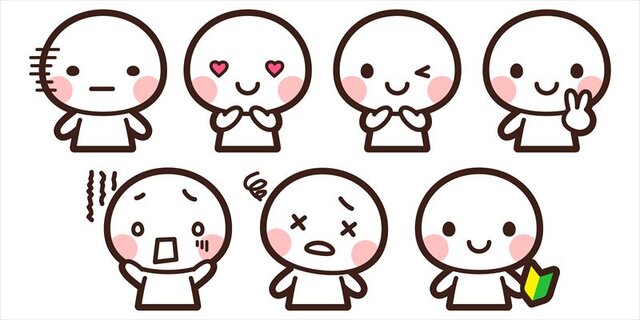夫婦の生活費はどれくらい?年代別の相場やお金の管理方法を解説
夫婦で使う生活費は、どれくらい掛かっているものなのでしょうか。
毎月節約しているつもりでも、カツカツになってしまうのは使いすぎている可能性も考えられます。
ライフイベントによっても生活費は変わってくるため、年代によっても異なるわけです。
年代別の相場や、賢いお金の管理方法などについて解説していきます。
ライフイベントによっても生活費は変わってくるため、年代によっても異なるわけです。年代別の相場や、賢いお金の管理方法などについて解説していきます。
夫婦で暮らす生活費の相場
夫婦で暮らす生活費の相場や内訳などを参考にして、比較してみましょう。
夫婦2人暮らし
子供の人数や年齢によっては、もう少し支出が多くなることもあるのであくまで相場です。高校や大学などへの進学となれば、教育費の出費が増えることになります。
子供がいる上に両親との同居となった場合は、さらに出費が増えることがわかっているので、同居の場合は生活費の負担をどうするか決めておくことがおすすめです。
都心と地方の違い
首都圏エリアの家賃は、地方と比べて高いため負担になることが考えられます。勤務先で交通費を支給されるのであれば、郊外に住んで節約することもできますが、そうでない場合は交通費がかさむことになります。
一方地方では、家賃が抑えられても交通費や車の維持費がかさむこともあるため、トータル的には変わらないこともあるんです。ただし、首都圏は娯楽などが多いことから、つい出費がかさむということもあります。
生活スタイル別の生活費
収入と支出のバランスは、働き方や住居が大きく関係します。
生活スタイル別の生活費について、みていきましょう。
夫婦共働きの場合
子供がいる場合の総支出が34万円ほどでも、共働きなら多少出費が増えても余裕があることがわかります。夫婦ともに正社員として働いていれば、年収の中に賞与などもあるため貯蓄に回すことが可能です。
夫のみが働いている場合
総支出を考えると、10万~15万円ほどしか余裕がないため共働きと比べると貯蓄に回す余裕が減ってしまいます。特に子供がいる場合は、教育費などが増えていくことのなるため支出が増えていくでしょう。
共働きの夫婦よりも夫だけが働く夫婦は、支出が2万円ほど下がりますが収入の差を考えると可能であれば共働きが理想だと言えます。
持ち家か賃貸か
固定資産税や修繕費以外のコストがかからないため、毎月の支払いが発生しません。賃貸物件でも住宅を購入した場合でも、毎月の支払いが発生しますが、住宅の場合であれば資産として残ることがメリットです。
住宅を購入したくても転勤が多いなど理由がある場合は、家賃を抑えながら貯蓄をしていくことが良いと言えます。
年代別による生活費の相場と内訳
20代と40代では、支出の内訳が異なるポイントがあります。
年代別による生活費の相場と内訳について、みていきましょう。
20代の生活費
しかし、20代が他の世代と比べて支出が高いのは住居費となっています。結婚して間もないことから、賃貸物件に住むケースが多く家賃の出費が他の世代よりも高いことが特徴です。
ただし、統計には住宅ローンが含まれていないため結果的にはあまり変わらないことになります。20代で子供がいない場合は、あまりライフステージがないため比較的支出を抑えられる傾向があると言えるでしょう。
30代の生活費
住宅ローンとともに、マイカー購入するケースも出てくるため交通費も高くなり、子供が増えたことで衣類費も高くなっています。そして、子供が増えて幼稚園や保育園などに通わせる教育費も発生するようになっていることが特徴です。
相場が約26万円ですが、住宅ローンを組んだ場合はプラス3~5万円して考えておくと良いでしょう。
40代の生活費
さらに、学習塾などに通わせることで教養費も高いことが特徴です。20代、30代と年齢を追うごとに食費が上がるのは、子供の成長によるものとなります。
50代までは40代と同じ傾向がみられますが、60代以降の支出は年々低くなるのは、子供が成長したことやローンが完済していることなどからです。
夫婦でお金の管理をする方法
上手なやりくりで貯蓄を増やすためには、お金の管理方法が大事なポイントとなります。夫婦でお金の管理をする方法について、みていきましょう。
1つの財布でお金を管理する
1つの財布で管理すると、お金の使い方が明確になるため管理がしやすいことがメリットです。貯蓄をいくらにするかなど、話し合って決める際もわかりやすくなります。
1つの財布で管理をするデメリットは、夫婦でお金の使い方が異なることです。デメリットを避けるためには、結婚前に2人できちんと話し合っておくようにしましょう。
財布を2つに分けて管理する
収入が同じくらいであれば良いのですが、差がある場合片方の負担が大きくなることがデメリットです。そして、残ったお金を自由に使えることは良いことですが、使いすぎて貯蓄ができないという可能性もあります。
財布を2つにする場合は、使うお金と貯蓄する金額についてしっかり話し合っておくことが重要です。
片方の収入を貯金にしてどちらかを生活費にする
給与をそのまま管理できるので、非常にわかりやすいと言えます。ただし、給料のバランスによっては分けることは難しいことがデメリットです。
給料が同等もしくは、どちらかが極端に低いと分けることは難しくなります。夫が35万円~ほどであれば、生活費にちょうどいいバランスとなるでしょう。
上手な節約方法
気づかずに使いすぎてしまっているものをみつけて、上手に節約していきましょう。
生活リズムを合わせて節約
少しのことですが、お互いにバラバラの時間で使ってしまうと二重に電気代や水道代がかかることになるからです。残業が多いなど理由があれば仕方ありませんが、可能であれば好きな時間ではなく一緒に行動することをしていくだけで、固定費が変わってきます。
食費の見直しをする
ランチであれば、外食ではなくお弁当を作るようにすればコストが下がる上にヘルシーです。そして、行きあたりばったりで買い物に行くのではなく、ある程度必要な物を計算して買うように計画することも節約につながります。
冷蔵庫にあるものを優先して消化していく、作り置きをするなどちょっとした工夫で食費はだいぶ節約可能です。毎回作るものを決めて買い物をしていると、余分な買い物が増えてしまうので、冷蔵庫の材料からレシピを考えるようにしましょう。
定期的に話し合う
そのため、定期的に夫婦で話し合うことが大事というわけです。現時点の方法で良いのかどうか、毎回状況と合わせて見直すようにしましょう。
問題点に気づかずお金の管理をし続けてしまうと、貯蓄が増えなかったり生活費が足りなくなったり不具合がでてきます。
そんなことにならないためには、定期的に話し合う機会を持って夫婦一緒に貯蓄を増やしていきましょう。
夫婦の生活費を見直して賢く貯蓄をしていこう
収入と支出のバランスが良いのか悪いのか、夫婦で話し合いながら見直していきましょう。