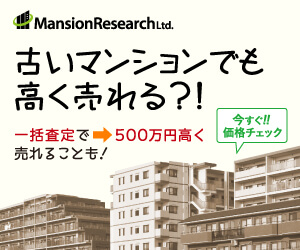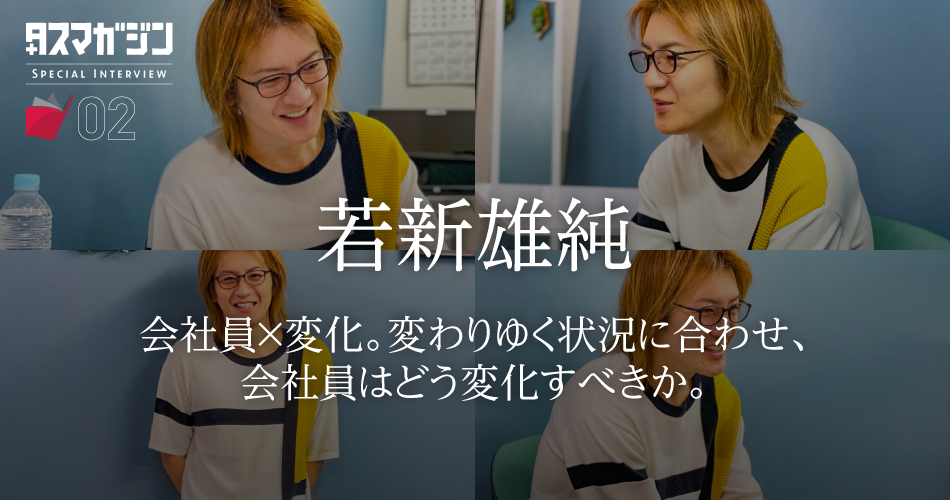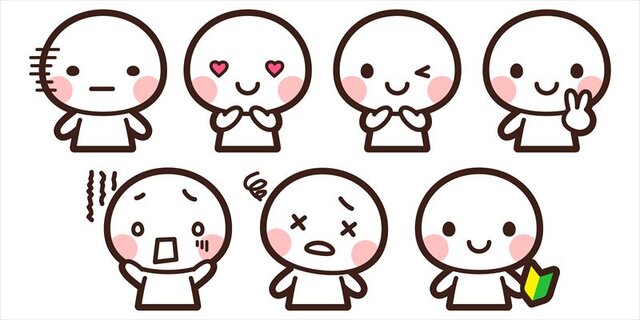利回りと金利、利子と利息の違いって?金融用語について知っておこう!
お金を銀行に預け入れる際など、金融関連で良く見聞きする機会が多い言葉として、「利回り」・「金利」、「利子」・「利息」といったものがあります。どれも私たちもよく使う、馴染みがある言葉のようで、実は具体的にはどんな違いを持っているのか分かりづらい用語です。それぞれの用語の意味や、使い方の違いについて知っておきましょう。
金融用語の違いを知っておこう!

金融用語としてよく見かける「利回り」や「金利」、「利子」や「利息」等があります。投資をする上で知っておきたい、それぞれの用語の詳しい意味や、違いについて知っておきましょう。
「利子」と「利息」の違いとは?
「利子」と「利息」は、それぞれの表記は違っていますが、根底にある意味としては、実は同じことを指しています。どちらとも、金銭を貸し借りする際に発生する「対価」のことを指す言葉です。
法律などでの使われ方の違い
お金の貸し借りにおける決まりを定めている利息制限法などでは、「利息」に統一されています。法律にならい、クレジットカードのキャッシングなどでも利息が用いられています。
所得税についての決まりを定めている所得税法などでは「利子」という言葉が使われています。
「利子」も「利息」も金額のことを表していることに注目しましょう。そのため、利子〇%という使い方は、本当は適当ではないと言えます。
金融機関での使われ方の違い
金融機関によっても、この2つの言葉の使い分けがされていることがあります。銀行に預け入れた預金には「利息」が用いられています。
そして「利子」は、ゆうちょ銀行で預け入れた貯金に対して使われています。また、多くの金融機関で取り扱っている住宅ローンの場合は「利息」を用いられていることが多いようです。
慣用句的な違い
元々は同じ意味を指す言葉なのですが、私たちが普段使う慣用的な表現として、以下の使い分けをしていることもあります。
お金を借りる際に元本に加えて貸し手に支払う金額
お金を貸した際に元本に加えて借り手から受け取る金額
つまり、貸している側か、借りている側かという立場の違いによって使い分けていることが多いと言えます。
「金利」と「利回り」の違いとは?

「金利」と「利回り」も、金融関連で良く使われています。そして、上記の「利子」や「利息」とも意味はよく似ています。
そして「金利」は、金銭を貸し借りする際に、元本に対してのパーセンテージ、つまり割合のことを指しています。
「利回り」の具体的な例とは?
たとえば株式を10万円で購入して半年ほど経った時に、配当金として1,000円を受け取りました。さらに半年経ち、その株式を10万9,000円で売却をしたとします。
利益は、株式の売却益である9,000円と配当金の1,000円で、合計1万円となります。投資額が10万円に対して、利益が1万円生じたことになります。投資額に対するパーセンテイジを算出して、利回りは10%だと言えるのです。
「利回り」は、銀行の定期預金などの「金利」と同じように思えます。たとえば、1年ものの定期預金に同じ金額を元本として預け入れた場合で考えると、最初の1年は「金利」も「利回り」も同じ金額となります。
預け入れの1年という期間が満期になると金利が付きます。金利も含めて預け入れをさらに継続する選択をしていれば、金利がさらに金利を生み出すことになりますので、2年目以降は「利回り」と「金利」とのパーセンテージが異なってくるのです。
「単利」と「複利」とは?
金利にも単利と複利があります。
銀行の定期預金の場合は単利型、複利型、どちらのタイプもあります。同じ商品でも、元本だけに利息を付ける単利か、利息を含めて利息を付ける複利で受け取るか、選択することができるタイプもあります。
金融用語の違いや使い方を知っておこう!
「利子」と「利息」は、もともとは同じ意味を指す言葉ですが、法律や慣用的な意味では異なる使い方をすることがあります。
「利回り」と「金利」は、どちらもパーセンテイジを指す言葉であることに注意しましょう。日ごろ何気なく見聞きしている金融商品に関する用語を知っておくことで、投資の際に役立てて、投資をする際に役立ててみましょう。